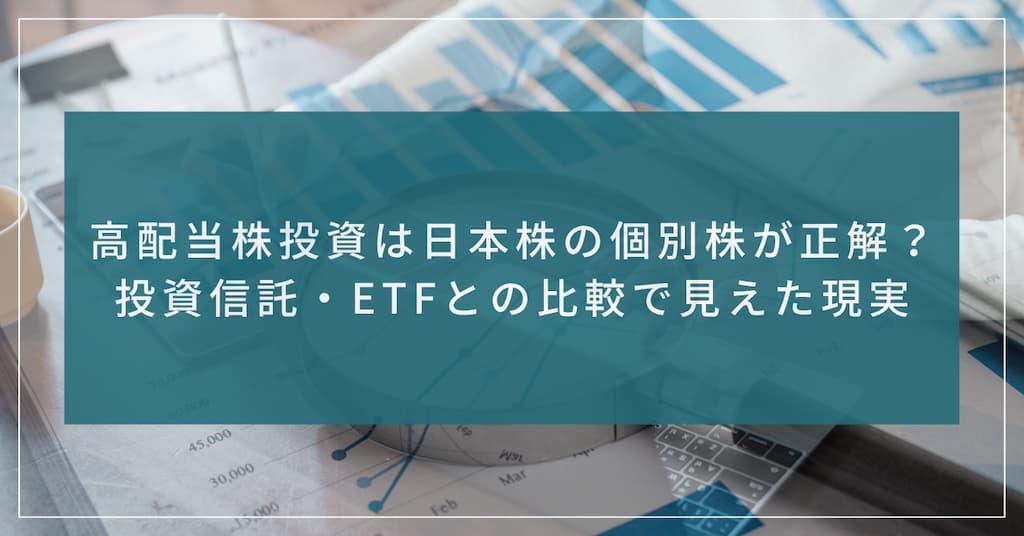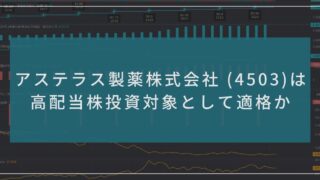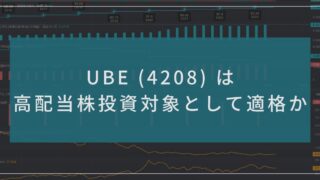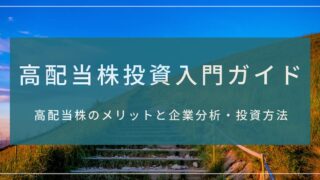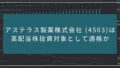高配当株投資を始めたいと思ったとき、ETFや投資信託は手軽で選ばれがちです。
しかし、実際に中身を分析していくと、高くない配当利回り、信託報酬の高さ、罠銘柄の混入、税金面での不利といった「落とし穴」が見えてきます。
本記事では、3つの選択肢を徹底比較したうえで、高配当株投資をするなら日本株の個別株投資が最も堅実で納得感のある選択肢だと考える理由を詳しく解説します。
高配当株に投資するには?─3つの代表的な選択肢を整理しよう
インデックス投資を続けてきた方の中には、「積立投資にも慣れてきて、次の一手を検討したい」と感じ始めた方もいるかもしれません。
そんなときに気になるのが「高配当株投資」です。
配当金という「使えるお金」が定期的に手に入ることで、日々の選択肢が広がっていく実感が得られるのが魅力です。
高配当株投資には、主に3つの手段があります:
| 投資手段 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 日本株の高配当投資信託・ETF | 配当が低く、手数料が高め。組み入れ銘柄に「罠銘柄」が混ざっている場合も。 |
| 米国株の高配当ETF | 優れた商品が多く、分散性も高いが、税制面で不利。 |
| 日本株の個別株投資 | 構成の自由度が高く、企業分析も楽しめる。 ただし、情報収集やリバランスの手間もかかる。 |
この記事では、これらの選択肢について比較します。
日本の高配当株ファンドを比較して見えた、割高なコストと控えめな利回り
日本の高配当株ファンドは「高配当」をうたっていますが、実態を見れば利回りは控えめで、コストや中身にも多くの課題があります。
ここでは代表的なETFと投資信託を比較し、その落とし穴を整理します。
【1478】iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF:堅実設計だが「高配当感」は薄め
まずは、ブラックロックが提供する「1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF」の概要を確認してみましょう。
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETFは、MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)への連動を目指すETF(上場投資信託)です。
BlackRock 1478 iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF公式ページを引用
MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)は日本国内の取引所に上場している大型・中型株を対象とした配当継続性や配当性向、財務体質(ROE、負債・自己資本比率、収益の変動性)等の基準を満たした企業の中から、MSCIジャパン指数の配当利回りの130%を超える利回りを持つ銘柄を構成銘柄として算出される時価総額加重平均型の指数です。
ただ利回りが高いだけの銘柄を並べるのではなく、財務健全性も考慮されている点は好印象です。
とはいえ、過去12ヶ月の分配金利回りは2.55%(2025年6月時点)と控えめ。名前の印象とは裏腹に、「高配当」とは感じにくい水準です。
また、2025年1月の保有割合1位・60億円保有していた任天堂が、6月時点で除外されている点も気になります。
指数との連動性を維持するためとはいえ、こうした銘柄の入れ替えは売買コストを発生させます。
信託報酬に含まれない隠れコストとしてパフォーマンスに負の影響を与えうるのが懸念です。
さらに、信託報酬は年率0.209%。オルカン(0.05775%)の約3.6倍にもかかわらず、構成銘柄は31社のみと、分散性には疑問が残ります。
【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 ETF:配当性向のみで選別した銘柄パック
次は、野村アセットマネジメントが提供する【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 ETFの概要を見ていきましょう。
日経平均高配当株50指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指します。
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信公式サイトより引用
※日経平均高配当株50指数は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。計算には配当を加味しています。
2025年6月19日時点の分配金利回りは3.88%と高水準で、見た目のインパクトはあります。
ただし、中身は日経平均採用銘柄の中から単純に配当利回り上位50社を選ぶだけ。
財務の健全性や配当の継続性は考慮されておらず、アステラス製薬やUBEなどの“罠銘柄”が含まれています。
📚関連銘柄の分析記事もあわせてご覧ください:
加えて、信託報酬は0.308%とやや高めでオルカンの5.3倍のコスト。
また、より選定基準が丁寧な【1478】ETF(0.209%)と比べてコストが高いことに疑問が残ります。
日経平均高配当利回り株ファンド(投資信託):人気はあるが低利回り&リスク管理に難あり
最後に、「日経平均高配当利回り株ファンド」について見ていきましょう。
主として日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。
信用リスク懸念や無配懸念があると委託会社が判断した銘柄は、投資対象銘柄から除外することがあります。
楽天証券では、2025年6月時点で積立設定件数ランキング9位・買付ランキング14位と、人気のあるファンドです。
しかしその中身を見ると、疑問が湧いてきます。
まず、2025年6月20日時点での利回りはわずか2.0%。
また、「信用リスクや無配懸念のある銘柄は除外」とあるものの、2024年12月末時点の組入2位はその後無配となった日産自動車。これを組み入れていた実績は、ファンドの判断基準への不安につながります。
日産の株価も大きく下がっているので、分配金も基準価額も減る (資産が目減りする)という本末転倒な状態にもなりかねません。リバランス時の売買コスト(隠れコスト)も積み重なり、利回り以上に実質的なリターンが削られるリスクがあります。
さらに信託報酬は0.693%(税込)とオルカンの12倍のコストがかかっています。
予想配当利回りの上位30銘柄から選定しているだけの投資信託に見合う金額を払かは甚だ疑問です。
まとめ: 3つのファンドを比べてわかった、日本の高配当ファンドの落とし穴
ここまで紹介してきた3つの高配当ファンド(+参考として日経225連動型ETF)を表で整理しました。
| ファンド名 | 利回り | 信託報酬 | 差引利回り | 銘柄数 | 方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1478】iシェアーズMSCIジャパン高配当利回りETF | 2.5% | 0.209% | 2.29% | 31 | 財務健全考慮 |
| 【1489】NEXT FUNDS 日経平均高配当株50 ETF | 3.9% | 0.308% | 3.59% | 50 | 利回り順 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド(投資信託) | 2.0% | 0.693% | 1.31% | 30 | 利回り順 |
| 【1321】NEXT FUNDS 日経225連動型 | 1.49% | 0.10527% | 1.38% | 225 | 日経225採用銘柄 |
これらの比較から見えてきた、3つの「落とし穴」は以下の通りです。
- 「高配当」と言っても利回りはそこまで高くない (4%に届かない)
- 信託報酬が重く、実質利回りをさらに削る
- 配当利回り順で銘柄を選ぶロジックが危うい (次セクションで詳細解説)
これらを踏まえると、特に「日経平均高配当利回り株ファンド(投資信託)」は、差引利回りが日経225全体に投資する1321よりも低い点が致命的です。
配当利回りでも銘柄分散(リスク低減能力)でも負けているので、敢えてこの投資信託を購入する必要はないでしょう。
一方で、1489は利回りが高いため気になりますが、次のセクションで「配当利回り順で銘柄を選ぶロジックが危うい」点を解説しつつ、私なら選ばない理由について深掘りします。
なぜ「配当利回り順のETF」は危ないのか?
一見するとシンプルでわかりやすい「配当利回り順ETF」ですが、その裏には意外なリスクが潜んでいます。ここでは、その構造的な危うさを解き明かします。
利回りが高く見えるのは「株価が下がったから」かもしれない
配当利回りは「直近の配当金 ÷ 株価」で決まるため、株価が大きく下がった銘柄は見かけ上の利回りが急上昇します。
例えば日産自動車は、2024年3月時点では配当金20円、株価600円で配当利回りは3.3%でした。
その後、2025年2月には株価が430円に下がり、配当利回りは4.6%に上昇。
しかし、2025年4月から無配に転落し、配当利回りは0%となりました。
このように、利回り順に銘柄選定することで、罠銘柄を組み入れてしまう点が「配当利回り順ETFの弱点」です。
自動リバランスで罠銘柄を拾い、優良株を手放す構造
配当利回り順ETFは、定期的に自動リバランスします。
株価が上昇し利回りが低下した企業は除外され、逆に株価が下がり利回りが高く見える企業は新たに組み入れられます。
しかし、この仕組みでは「成長可能性のある企業を早めに売り、減配リスクの高い罠銘柄を拾う」という期待しない動きが繰り返されます。
実際に、過去には日産のような企業が組み込まれており、最近では業績が悪化しているアステラス製薬が組み入れられており、私は危険な構造だと思います。
高配当でもなく、資産も増えづらい――日本株高配当ETFの現実
利回り順ETFは「思ったほど高配当ではない(4%未満)」という現実がありましたが、資産推移はどうでしょうか?
2025年6月時点では、資産増加率は VT(全世界分散)→ 1321(日経225)→ 1489 の順です。

高配当株投資では「資産が大きく増えなくても配当があればいい」と考える人も多いでしょう。
しかし、ここで問題なのは「さほど高配当でもない上に資産が増えていない」点です。
加えて、1489は構成銘柄の9割が景気敏感株で占められています。そのためボラティリティが高く、不況時にメンタル面で悪影響を受ける可能性が高いです。
さらに、1489は2017年2月に設定された比較的新しいファンドで、これまでの好調は2020年以降の商社・銀行など日本の景気敏感株が強かった特殊要因が大きく影響しています。
今後も比較的良いパフォーマンスを維持できるかは未知数です。
つまり、「さほど高配当でもなく、資産も増えづらい」――これが、利回り順ETF(特に1489)の現実なのです。
配当利回り順ETFは避けるべき。日本株は個別株が無難
そもそも高配当株投資は「財務優良で長期的に配当支払できる企業を、配当利回りが高い“タイミング”で買う」ことが重要だと私は考えています。
しかし、利回り順ETFは利回りを使って銘柄選定をしているため、本来のツールの使い方を間違えているように見えます。
価格が下がることで高配当になった罠銘柄を含んだポートフォリオを構築し、さらに入れ替え時の不要なコストを負担することになります。
だからこそ、1) 財務健全性を重視するETF(例: 1478)を高配当利回りのタイミングで購入するか、2) 自分で個別株を分析して高利回り時に買うか、二択になると私は考えています。
ただし、前のセクションで解説した通り、方針 (1) の財務健全性を重視するETFは高配当状態ではないので、現実的には (2) が適切な選択肢だと考えています。
米国の高配当ETFは魅力的に見えても、税制上のデメリットに注意
米国の高配当ETFは、一見すると高い配当利回りが魅力的に映ります。しかし、日本に住む投資家にとっては、思わぬ落とし穴があります。
VYM・HDV・SPYDの特徴と人気の理由
米国高配当ETFは「安定したインカム収入を得たい」人に人気です。
- VYM:大型かつ高配当の安定企業に幅広く投資。
- HDV:財務健全性を重視した厳選銘柄。
- SPYD:配当利回り上位80銘柄に均等投資。
これらは財務健全性なども考慮された優れたETFであり、日本の高配当ETFにもこのレベルの商品が欲しいと感じるほどです。
配当利回りが4%前後になることもあり、表面的には非常に魅力的に見えます。
外国税額控除・二重課税・税引後利回りの落とし穴
日本居住者の場合、米国でまず10%の課税がかかります。例えば配当利回りが4%の場合、3.6%に減少します。
さらに、日本で約20%の課税がかかるため、最終的な手取り利回りは約2.88%にまで低下します (日本株の場合も20%の税金はかかりますが)。
外国税額控除を使うことで米国での課税を取り戻せますが、確定申告が必要で控除枠にも上限があります。
このように、税制面の影響で実際に受け取れる金額は目減りしてしまうが実情です。
また、新NISAでは外国で課税される税金は非課税にならないので、その点も注意が必要です。
日本から投資する場合の使いどころと限界
「通貨分散をしたい」という考え方で米国ETFを選ぶ人もいます。
ただ、その目的であれば、高配当ETFではなくキャピタルゲインを狙えるVTなどの全世界株式ETFに投資すれば良いのではないでしょうか?(VTも配当金に米国で課税されますが..)
税制面を考えると、外国株で高配当を狙うよりも、国内株で高配当を狙うほうが効率的で、結果的に手取りが多くなると私は考えています。
個別株投資は手間がかかるが、手数料削減と企業理解が大きな魅力
個別株投資は「楽して稼げる」とは程遠い選択肢ですが、その分、ETFでは味わえない解像度の高い企業理解と納得感、そして信託報酬を払わなくて済むという大きなメリットがあります。
「手間を惜しまず、自分の判断で企業を選びたい」という方にとって、個別株投資は単なる資産運用を超えた充実感をもたらす選択肢になります。
個別株投資のメリットとデメリットを整理する
個別株投資の魅力は、なんといっても自分の目で選んだ銘柄を納得して保有できる点にあります。ここでは具体的なメリットとデメリットを整理してみましょう。
- 財務状況を見て、納得して選べる
- タイミングを見計らい、高い利回りを狙える
- 信託報酬(手数料)が不要
- 優待や株主イベントを楽しめる
これらのメリットを活かすことで、ETFよりも盤石で高い利回りのポートフォリオを構築できます。
さらに、信託報酬を抑えることで追加の株を購入できる点も大きな魅力です。
例えば、1489に100万円投資すると年間3,080円の手数料がかかりますが、その分を使ってNTT株を20株追加購入できます。
また、株主優待はあくまでおまけですが、普段は入れない施設の見学や、割引券をもらえるのは地味に嬉しいポイントです。
- 銘柄分析には最低でも3〜4時間程度の時間が必要
- 分散投資には資金が必要(S株で1株つず買えばハードルは下げられる)
- 定期的にポートフォリオをメンテナンスする必要がある
こうした分析や管理に手間をかけたくない方、本業に集中したい人には ETF・投資信託(特にVTやオルカン)を活用したインデックス投資が現実的です。
ただし、分析の軸を掴んでツールを使うことで手間を減らすことも可能です。こちらの高配当株投資入門ガイドでも詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
企業の数字を読む面白さと、知的好奇心を満たす楽しさ
個別株投資の醍醐味は、企業の数字の裏にある物語を読み解けるところにあります。
IR資料や決算短信を読み込み、どの事業が利益を生んでいるのか、どんな戦略で成長を目指しているのかが見えてきます。
さらに、企業の歴史や将来戦略を見つめることで、日本企業の底力を理解できるようになります。
「企業を見る旅」という感覚を楽しみながら投資を続けられるのは、個別株ならではの魅力です。
少額から始めたいならS株という選択肢も
「個別株投資は面白そうだけど、いきなり大きな資金を投じるのは不安…。資金面で分散も難しいし。。」という方には、S株という選択肢があります。
S株なら1株から購入できるため、分散投資のハードルが一気に下がります。
まずは気になる企業を少しずつ買ってみて、実際に配当を受け取りながら学んでいくのもおすすめです。
▼S株に関して詳しい記事はこちら
まとめ|高配当株投資をするなら日本株の個別株投資
ここまで、高配当株投資の3つの代表的な手段を見てきました。
結論として、高配当株投資をするなら日本株の個別株投資が最もおすすめだと私は考えています。
理由は以下の通りです。
- 日本株の高配当投資信託・ETF: 利回りは低く、手数料も高く、罠銘柄を取り込みやすい構造
- 米国の高配当ETF: 税金面で不利で、最終的な手取りが減る
- 日本の個別株: 手間はかかるが、手数料を抑えて堅実な高利回りを狙える
一方で、個別株の分析に時間をかけたくない、投資を完全に自動化したいという方には、
高配当株投資は一旦置いておいて、手数料や税金で損をしづらいVTやオルカンといったインデックスファンドを使う選択肢が現実的です。
✅ Next Action
「個別株の分析に挑戦してみたい」と思った方は、以下の記事で分析の基本方針や時短テクニックを詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。