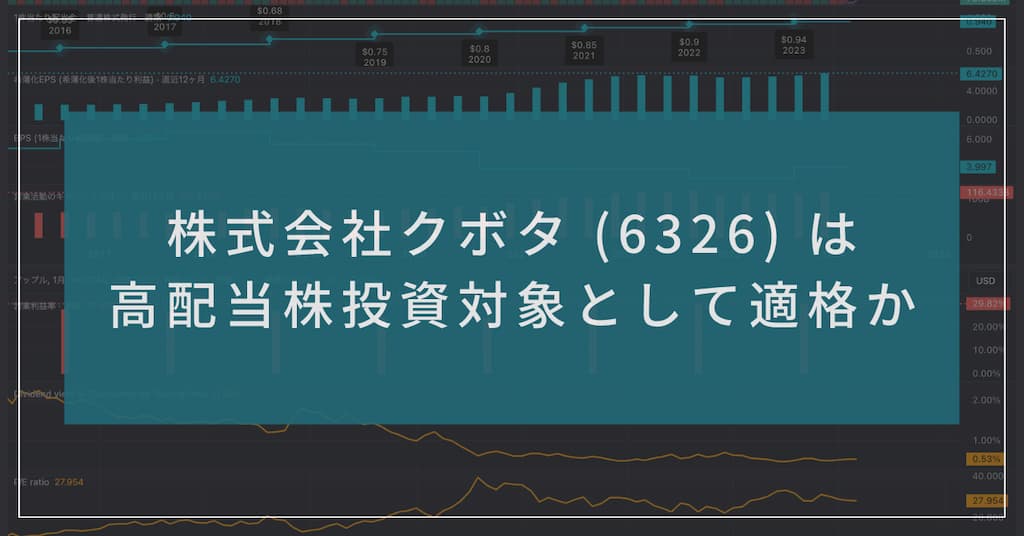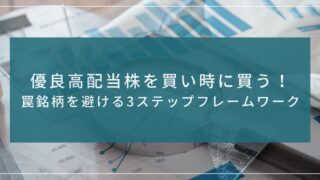130年以上にわたり「食料・水・環境」を支えてきた老舗メーカー、株式会社クボタ(6326)。
農業機械や水インフラを手がけ、世界120か国以上で事業を展開するグローバル企業です。
財務体質は堅牢で、減配のない安定配当を続けており、長期保有にも安心感があります。
一方で、営業キャッシュフローの波やROIC(資本効率)の伸び悩みなど、「稼ぐ力」の面では課題が残るのも事実。
高配当株として魅力を感じる水準(配当利回り4%)には届かず、現状では「高配当優良銘柄でも高配当罠銘柄でもない」中立的なポジションにあります。
この記事では、決算短信とTradingViewのデータをもとに、クボタ株が高配当株投資対象として適格かを徹底分析します。
クボタは「高配当株投資対象として優良銘柄でも罠銘柄でもない」手堅い銘柄。
今は静観し、営業CF・営業利益率・ROIC 改善の兆候が見えたタイミングで再評価を検討。
企業分析の方針は十人十色ですが、私の方針については以下の記事でまとめています。株式投資が本業でない社会人でも現実的な時間で分析する方法なので、本記事と併せてご拝読ください。
なお、この記事は参考程度にしていただき、投資は自己責任でお願いします。
私も日々勉強していますが分析方針が万全とは限りません。より良い分析アイディアなどありましたら、X (旧 Twitter) で議論できますと幸いです。
※ 本記事は企業分析ツールの画像を多用しており、可能な限り大画面での閲覧をお勧めします。
会社概要
クボタは1890年創業の老舗メーカーで、130年以上にわたり「食料・水・環境」という人々の生活を支える分野に取り組んできました。事業は2本柱。
- 農業機械・建設機械・エンジンを扱う機械事業
- ダクタイル鉄管・ポンプ・環境プラントなどを手がける水・環境事業
世界120カ国以上で事業を展開。農業機械の累計生産台数は510万台を超え、長年にわたって世界の食料生産を支えています。
水・環境分野でも、水道管や水処理プラントを通じて国内外のインフラ整備に貢献。
持続的な社会需要に支えられた安定基盤を持ちつつ、中期計画では北米建機・ASEAN農機の拡販、水ソリューション事業の転換など、次の成長ステージを見据えています。
3 つの必須条件(配当金・利益・資産の上昇傾向): クボタは満たしている
結論:3項目すべてクリア。高配当株投資対象として適格かを詳細調査する価値のある企業です。
下のグラフは、TradingViewで取得したクボタの1株あたり配当金・1株あたり純利益(EPS)・1株あたり純資産(BPS)の推移を示したものです。
2006年ごろからの約20年分のデータを視覚化しており、配当・利益・資産のいずれも長期的に右肩上がりであることがわかります。

配当金が上昇傾向か: 安定増配を継続
2011年以降は一貫して上昇傾向を維持し、現在は 50円。長期保有の安心感があります。
利益が上昇傾向か: EPS は長期的に上昇傾向、直近での伸びが顕著
1株あたり利益は長期的に上昇傾向。特にここ数年で130円台から190円台へ大きく上昇しており、利益水準の成長が確認できます。
ただし、自社株買いの影響もありそうなので、詳細調査ではキャッシュフロー面も合わせて確認しておきたいところです。
資産が上昇傾向か: BPSは2010年以降右肩上がりに拡大
BPS(1株あたり純資産)は2010年以降ほぼ一貫して上昇を続け、直近では2,000円を超える水準に到達。
内部留保の積み上げにより、企業体力の厚みが明確に見て取れます。
6 つの望ましい条件: 営業 CF と資本効率には課題あり
結論:6項目中3項目クリア。財務は極めて健全だが、営業CFと資本効率に課題あり。
クボタを定量・定性の両面から整理すると、全体としては財務体質が健全で配当維持力も高く、安定感のある企業といえます。
一方で、本業の稼ぐ力や資本効率の面では、やや改善余地が残ります。
| 項目 | 評価 | 1文サマリー |
|---|---|---|
| 本業の稼ぎ(営業CF) | △ | 2022・2023年はマイナス、2024年は一時的要因で改善。 |
| 稼ぎ方の効率(営業利益率・ROIC) | △ | 営業利益率は安定も、ROICは6〜8%台で資本効率に伸び悩み。 |
| 財務の健全性(自己資本比率・ICR) | ○ | 自己資本比率41%、ICR3.7倍で健全。 |
| 配当余力(配当性向・キャッシュ配当性向) | △ | 帳簿上は健全だが、現金ベースでは慎重姿勢が必要。キャッシュ配当性向79% |
| 株主還元姿勢(累進配当・自社株買い) | ◎ | 総還元性向50%を明言。還元姿勢は非常に積極的 |
| 不況耐性(リーマン・震災・コロナ期) | ◎ | 主要不況期すべてで減配なし。配当維持力は極めて高い。 |
本業で稼いでいるか: 営業CFがマイナスの年もあり要経過観察
下のグラフは、2006年以降の営業利益・営業キャッシュフロー・営業利益率の推移を示しています。

営業利益は2024年以降に大きく改善しており、これは決算短信にもあるように、製品価格の値上げ効果および為替の改善が寄与したものです。
値上げした製品は価格を下げにくいため、今後も一定の収益改善効果が持続する可能性があります。
一方で、営業キャッシュフローは2023〜2024年にかけてマイナスへ転落。
短信によれば、これは支払条件の変更(支払サイト短縮)に伴う支払い前倒しが主因であり、本業の収益力が低下したわけではありません。
2025年には約2,800億円まで急回復していますが、これは「前年の反動」と「運転資本の改善」による一時的なプラス要因のようです (2024年12月期決算短信参照)。
また、2024年度の決算説明会資料では、主要市場である日本・北米・欧州のいずれも“低迷・減少”という表現が散見されます。このことから、足元の営業利益改善が持続的成長に直結しているとは言い切れず、また、営業CFの安定化には引き続き経過観察が必要といえます。
→ △(営業利益が増加するか・営業CFの回復が持続するかを要経過観察)
稼ぎ方が上手いか: 営業利益率は10%前後で安定も要経過観察
前のセクションで触れた通り、クボタの営業利益は2024年度に増加しましたが、これは主に製品価格の引き上げと為替差益によるものであり、営業利益率そのものは約10%前後で推移しています。
この数値は近年ほぼ横ばいで、利益率が構造的に改善しているとは言い難い状況です。
決算短信などで「営業利益率の改善が進まない理由」は明示されていませんが、各期の資料を総合すると、原材料や労務費の上昇、販売地域構成の変化、およびインフラ関連事業の低採算構造が背景にあると見られます。
値上げによって営業利益額は増加しても、こうした構造的要因により営業利益率は横ばい圏を抜け出せていません。
下のグラフは、2006年以降のフリーキャッシュフロー(FCF)・FCFマージン比率・ROIC(投下資本利益率)の推移を示したものです。

ROICはおおむね6〜8%台で推移しています。
一方、同業他社を見ると、コマツが約11.3%、日立建機が約8.4%と、クボタはやや見劣りする位置にあります。
なお、中期経営計画で掲げる「5つの重点テーマ」のうち、4つ目には明確に「利益率の向上」が掲げられています。
それにもかかわらず、決算短信や決算説明会資料ではこのテーマに関する進捗や具体的取り組みが主要項目として扱われていないのは、株主としてやや懸念を抱くポイントです。
利益率の向上を掲げながらも、その実現プロセスが説明されないことは、経営として「利益の質」をどこまで重視しているのかという姿勢を測りにくくします。
→ △(営業利益率10%前後・ROIC6〜8%。競合比較では見劣り、改善方針の説明も不足)
負債が多すぎないか: 財務は健全
クボタの財務基盤は総じて健全です。
自己資本比率は41.8%と、製造業の目安である40%を上回る水準を維持しています。
一方、インタレスト・カバレッジ・レシオ(ICR)は3.7倍。一般的には安全域にある数値です。
クボタの場合「営業キャッシュ・フロー ÷ 利払い」で算出されています。つまり、支払利息の約4倍程度の現金収入がある状態です。
2024年12月期の営業CFは過去最高の2,820億円で ICR は安全域にいるので、今後もこの水準を維持できるかどうかは注視したいところです。
→ ○(自己資本比率41.8%、ICR3.7倍。安全域を維持できるか要経過観察)
配当を出すときに無理をしていないか: 帳簿上は強いがキャッシュ面では不安も
クボタの配当は、帳簿上(利益ベース)では健全である一方、現金ベース(キャッシュフロー)ではやや慎重さが求められる構造です。
配当性向は25〜35%と適正範囲で、利益の成長に応じて着実に増配を継続。帳簿上の利益水準では問題はなく、健全な配当設計が続いています。
一方で、現金ベースでは不安もあります。以下はクボタの2022年度からのキャッシュの流れをまとめたものです。
| 年度 | 営業CF | 投資CF | FCF(営業+投資) | 財務CF | 期末現金等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ▲768 | ▲3,185 | ▲3,953 | +2,826 | 2,258 |
| 2023 | ▲1,727 | ▲1,734 | ▲3,461 | +1,784 | 2,221 |
| 2024 | +2,821 | ▲2,089 | +732 | ▲263 | 2,951 |
各年度のクボタ決算短信「連結キャッシュ・フローの状況」より
2022〜2023年はFCFが▲3,000〜▲4,000億円と大幅なマイナスで、その間の株主還元は借入や社債発行による財務キャッシュフロー(+2,000億円超)で賄われていると推測されます。
2024年は営業CFが+2,821億円まで回復し、投資CFを差し引いたFCFは+732億円と黒字転換。
ただし、配当支出は約580億円で、キャッシュ配当性向は約79%と、黒字化したばかりのFCFに対してはやや重たい水準です。
今後は、営業CFの持続力を確保し、キャッシュフロー黒字を安定的に維持できるかが増配余地の鍵となります。
→ △(帳簿上は健全だが、FCFベースでは慎重姿勢が必要。キャッシュ配当性向79%)
株主還元を大事にするか: 配当金・自社株買いを通した株主還元に積極的
クボタは、株主還元に明確に前向きな企業です。
株主還元ページによると安定配当の維持と向上を掲げ、総還元性向50%を目標に設定。さらに、取得した自己株式は即時消却を継続する方針を打ち出しています。
FCFがマイナスだった年度でも配当を維持しており、経営として株主への還元を重視する姿勢が明確です。
今後は、こうした積極的な方針をキャッシュフローとどう両立させるかが注目点です。
→ ◎(総還元性向50%を明言。還元姿勢は非常に積極的)
不況でも配当金を減らさないか: 不況時にも減配せずに乗り切る底力
クボタは、景気後退局面でも減配を行わない安定配当企業です。
リーマンショック、東日本大震災、そしてコロナ禍といった厳しい局面でも、一度も減配をせず、配当を維持または増配してきました。
利益やキャッシュフローが一時的に揺れても、配当を守り続けてきた実績は、長期投資家にとって大きな安心材料です。
→ ◎(主要な不況期すべてで減配なし。配当維持力は極めて高い)
2 つの買う条件 (トリガー条件)
結論:利回りでは届かず、割安性で補うタイプ。
配当利回りが 4% 以上か : 現状は水準不足、買いは“待ち”
TradingViewによると、クボタの直近12か月配当利回りは2.63%。過去レンジでは高めの位置にありますが、「高配当株」として投資対象にするにはやや物足りません。
還元姿勢は強いものの、営業CFや資本効率の弱さを考えると積極的に買う局面ではないといえます。
| 想定利回り | 目安株価 | コメント |
|---|---|---|
| 4.0% | 約1,250円 | 高配当水準として魅力が出始める水準。 |
| 3.5% | 約1,430円 | 長期保有を検討できる妥当ライン。 |
| 現状(2.63%) | 約1,900円 | 利回り的には投資妙味が限定的。 |
現状の株価(約1,900円前後)では、リスクに見合うリターンが得にくい印象です。
財務体質は堅実ですが、本業の稼ぐ力やキャッシュフローの安定性には改善余地があり、今は「買う」より「待つ」局面だと考えます。
→ △(配当利回り2.6%台。4%狙いなら1,250円程度が目安。現状は静観が妥当)
株価が価値に対して割安か: 利益水準とのバランスは取れている
PERは12.7倍、PBRは0.9倍。いずれも過去平均より低水準で、理論上は「割安」といえます。
ただし、利益率やROICの改善が進まない現状を考えると、この割安さは“成長期待の薄さ”を織り込んだ妥当な水準とも言えます。
本業の収益力が回復して初めて、株価の上値余地が見えてくるでしょう。
→ ○(PER・PBRともに割安。ただし成長性の低下で正当化される範囲)
競合他社分析
積極的に購入を検討するタイミングではないので、一旦競合他社分析は控えます。
今後コマツなどの競合他社を分析する中で、必要に応じて更新させてください。
今後への期待:収益構造の改善で再評価を狙える余地あり
クボタは財務面では安定していますが、今後の成長を考えるうえでは、「稼ぐ力」と「資本効率」の2点でどこまで改善できるかが鍵になります。
まず注目したいのは営業利益率の改善。値上げ効果だけでなく、原価低減や生産効率化などの取り組みを今後の決算で具体的に開示し、その成果を数字で示してほしいところです。
また、近年はフリーキャッシュフローの赤字が続いた時期もありました。
安定してプラスを維持できるようになれば、配当の持続性にも一層の安心感が生まれます。
さらに、ROICを同業他社並みの8〜10%水準に引き上げられれば、市場からの評価も変わってくるはずです。
地に足のついた成長戦略と、その成果が数字で確認できることを期待しています。
まとめ:今は“待ち”、改善が見えたら再評価したい銘柄
クボタは財務の健全性と配当維持力が光る、堅実な大企業です。
その一方で、いまの配当利回り(約2.6%)では「高配当株として買う理由」は弱く、優良高配当銘柄/高配当罠銘柄どちらにも当てはまらない中間ポジションと捉えます。良い会社だが、いまは価格も実力(稼ぐ力)も「買いの決め手」に欠ける——そんな位置づけです。
「6つの望ましい条件」は3/6クリア。残る3点、すなわち
- 本業の稼ぎ(営業CFの安定化)
- 稼ぎ方の効率(営業利益率・ROICの底上げ)
- 配当の現金面の余力(キャッシュ配当性向の引き下げ) の改善が確認できれば、評価は一段切り上がります。とくに、利益率改善の具体策と実績を決算で継続開示し、数字で裏づけられることが重要です。
投資判断としては「待ち」が妥当。利益率・ROIC・FCFの改善が数字で見えたタイミングで再評価して、配当利回り 4%(目安株価:約1,250円)付近で買えるのが理想的です。
クボタは「高配当株投資対象として優良銘柄でも罠銘柄でもない」手堅い銘柄。今は静観し、改善の兆候と利回り水準が整ったら買いを検討。
関連記事
1株ずつの購入は SBI証券の S 株がお勧めです。関連記事で複数証券会社の使い分け方を紹介しているので、1株ずつの購入にご興味がある方は併せてお読みください。