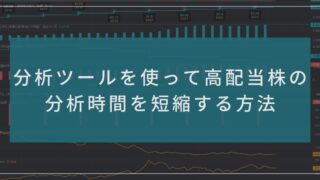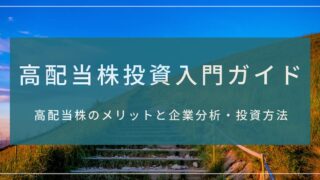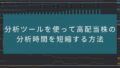高配当株投資はキャッシュフローの増える素敵な投資ですが、銘柄選びが難しくて悩んだことはありませんか?
私自身も最初は「配当利回りの高さ」だけを見て飛びつき、減配されたり、株価が下がり続けたりと、痛い目に遭いました。
失敗を経験しながら数年かけて試行錯誤と勉強を重ねた結果、罠銘柄を避けつつ、優良銘柄とその買い時を効率的に見つける「3ステップ分析フレームワーク」を作り上げました。
長期的に安定した配当収入を得るために、このフレームワークを使って「優良高配当株を買い時に買う力」を磨いていきましょう。
優良高配当株を適切なタイミングで買える3ステップ分析フレームワーク
高配当株には魅力的な利回りが多い一方で、業績が不安定な「罠銘柄」も数多く存在します。
罠銘柄は避けたいですが、高配当銘柄全てを詳しく分析するのは現実的ではありません。
そこで私が作り出したのが、3ステップで効率的に銘柄を絞り込み、詳細分析を行い、買い時を判断する「3ステップ分析フレームワーク」です。
- Step 13 つの必須条件でサッと選別
足切りイメージで、定量分析を短時間で済ませます。
- Step 26つの望ましい条件で分析し、長期保有向け優良株を見極める
Step 1 合格企業のみをじっくり分析。追加の定量分析やIR情報も活用します。
- Step 32つの条件が揃った買い時に優良株を購入
Step 1 & 2を通過した企業を、買い時に合わせて購入します。
この3ステップフレームワークを使うことで、効率よく罠銘柄を排除し、納得感を持って優良高配当株を選べるようになります。
それでは、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1|3つの必須条件で短時間に高配当株を絞り込む
まずは3つの必須条件を説明します。この条件を満たさない場合、投資対象からしばらく外します。
ざっくり言うと、配当金を払えて、稼げて、資本を蓄えられる会社を選ぶための基準です。
高配当株の必須条件① 配当金が上昇傾向
高配当株投資において最も重視すべきは、企業が配当金を長期的に減配せず、維持または増加しているかどうかです。
過去10年以上、配当金が維持・増加傾向にあるか(減配していないか)
この条件を満たす企業を選ぶことで、将来的にも安定した配当収入が期待できます。
高配当株の必須条件② 利益 (EPS) が上昇傾向
利益の成長は、企業が将来にわたって配当を安定的に支払うための土台です。
その指標として、EPS(1株あたり純利益)を確認しましょう。
EPS が長期的(5〜10年以上)に上昇傾向か
企業に利益成長の力があれば、将来の配当原資も確保しやすくなります。
EPS (Earnings Per Share / 1株あたり純利益) は以下の式で計算します。
EPS = 純利益/発行済み株式数
純利益は売上高から売上原価・販売費などを差し引き、営業外損益と特別損益を調整し、法人税等を引いた後の純粋な利益を指します。
このため、会計上の操作や一時的な損益の影響を受ける可能性がある点には注意が必要です。
EPSは純利益の増加を確認する上で便利な指標ですが、主に3つの注意点があります。
ステップ1ではEPSが右肩上がりであることをざっくり確認すればOKですが、ステップ2で「右肩上がりでも良くない場合」の詳細分析を行います。ここでは簡単にポイントだけ紹介します。
1つ目は、営業外損益(不動産の家賃収入など)や特別損益(資産売却益など)など本業以外で利益が底上げされている場合です。これは持続性が低いため、営業利益や営業キャッシュフローなどを併せて確認し、本業の稼ぐ力を見極める必要があります。
2つ目は、巨額のM&Aを実施している場合です。無形資産の減価償却など会計上の要因で純利益が一時的に押し下げられ、EPSが低く見えることがあります。この場合、詳細分析が必要です。
3つ目は、新株発行や自社株買いによる影響です。新株発行で分母が増えるとEPSは下がり、自社株買いで分母が減るとEPSは上がります。この場合、財務活動による影響か、本業による変動かを見極める必要があります。
高配当株の必須条件③ 資産 (BPS) が上昇傾向
株主資本の成長は、企業の安定性や配当の持続性を判断するうえで重要な基盤です。
その指標として、BPS(1株あたり純資産)を確認しましょう。
BPS が長期的(5〜10年以上)に上昇傾向か
BPSが右肩上がりであれば、企業が毎年の利益を着実に積み上げ、資本を厚くしてきた証です。
十分な内部留保がある企業は、たとえ一時的に業績が悪化しても配当を維持しやすく、また、将来の投資や不況時の備えにも資金を回すことができます。
そのため、減配リスクが低く、長期保有にふさわしい高配当株といえます。
BPS(Book Value Per Share)は以下のように計算します。
BPS = 純資産/発行済み株式数
ここでいう純資産とは、資産から負債(借入金などを含む)を差し引いた残りのことで、株主に帰属する会社の持ち分を表します。
BPSが毎年増加している企業は、利益を安定的に積み上げ、財務的な土台を強化している企業と判断できます。
これは、景気が悪化したときの備えや、将来の投資余力にもつながり、減配リスクを抑える観点でも重要なポイントです。
なお、BPSは以下のような要因で増減するため、変動要因を理解しておくことも大切です。
- 増える要因:利益の蓄積、配当の抑制、自社株買いなど
- 減る要因:赤字の継続、過剰配当、のれんの減損、希薄化など
「資産の厚み」という視点で企業を見るとき、BPSはとても有効な指標となります。
BPSが右肩上がりに見えていても注意が必要なケースもあります。ここでは代表的な2つをご紹介します。なお、ステップ1ではBPSが右肩上がりであることをざっくり確認すればOKです。
1つ目は、M&A後の「のれん(買収価格と実際の純資産の差額)」減損による資本の目減りです。
M&Aを実施すると「のれん」が資産として計上されますが、事業が期待したほどキャッシュを生み出していないと判断されると減損処理されます。
その結果、資産が大きく目減りしてBPSも減少します。
そのため、BPSが右肩上がりだとしても、M&A実施済み企業については営業キャッシュフローやROIC、売上や粗利率の推移などを定期的にチェックし、企業の実態を把握することが重要です。
2つ目は、1つ目と比較すると軽微ですが、BPSが増加していても実質的には資産の価値が目減りしているケースです。
たとえば、地方の土地価格が下落していても、帳簿上は取得価格のままであることが多く、含み損が可視化されません。
とはいえ、建物や設備は減価償却で徐々に価値を下げていきますし、土地価格の下落だけが対象となるため、影響は限定的です。
また、地価の実態把握には専門的な知識が必要なこともあり、私はこのケースについては詳しく調査していません。
ステップ2|6つの望ましい条件とIR分析で長期保有向け優良株を見極める
ステップ1で必須条件を満たした企業について、ここでは6つの望ましい条件を使って深掘りします。
IR資料や決算情報をもとに、本業の安定性や財務の健全性、配当の持続力などを多角的にチェックしていきます。
必須条件と望ましい条件の両方を満たした企業は、長期保有にふさわしい優良株候補としてリストに加えます。
本業でしっかり稼げているか?営業キャッシュフローを確認
営業キャッシュフロー(営業CF)は、企業が本業を通じてどれだけ安定的に現金を稼げているかを示す重要な指標です。
営業CFが直近5〜10年で右肩上がりになっているか
この傾向が見られれば、本業を通じて配当原資となる現金を継続的に生み出している企業と判断できます。
前のステップでは EPS を使って純利益の増加傾向を確認しましたが、その利益が本業から生まれているとは限りません。
純利益には、営業外損益(たとえば不動産の家賃収入)や特別損益(一時的な資産売却益など)も含まれるため、一見すると好調に見えるEPSでも、本業(営業利益)が低調なままの場合もあります。
こうした「帳簿上の利益」に惑わされないためにも、現金収支ベースである営業CFを使って本業の地力を確認することが有効です。
営業CFの最大の強みは、実際の現金の流れを反映している点にあります。
たとえば帳簿上では営業利益が出ていても、売掛金の回収が進まず現金が入ってきていない場合、営業CFは増えません。
このように、営業CFを確認することで、企業の現金回収能力や資金繰りの健全性までチェックできます。
さらに、大型のM&Aを実施した企業においては、もう一つの強みが活きてきます。具体的には、M&Aによって本業での現金収益が実際に増えたかどうかを可視化できます
M&Aで取得した資産には「無形資産」が含まれ、これらは減価償却費として一定期間かけて帳簿上の費用に計上されます。
しかしこの減価償却費には、実際の現金の流出は伴いません。すでに買収時になんらかの方法で支払い済みのため、毎年の会計処理はあくまで「帳簿上の減少」にすぎないのです。
営業CFは、損益計算書に記載された税引前当期純利益から、営業活動に直接関係しない項目を調整したうえで計算されます(間接法)。
このとき、帳簿上の費用である減価償却費は現金の流出を伴わないため加え戻されるのが特徴です。
そのため、買収後に営業利益 (帳簿上の利益) が一時的に低下していたとしても、営業CF (実際に稼いだ現金の動き)がしっかり増えていれば、M&Aが実際に現金収益につながっているかどうかを見極めることができます。
このように営業CFは、「見せかけの利益」ではなく本質的な稼ぐ力=現金の流れを把握できる重要な指標です。
高配当株を選ぶ上では、この指標で本業の健全性を必ずチェックしておきましょう。
稼ぎ方の効率は高いか?営業利益率とROICで見極める
効率的に稼げる企業は、景気の波に左右されにくく、持続的な配当を出し続けられる傾向があります。
この効率性を測る代表的な指標が、営業利益率とROIC(投下資本利益率)です。
- 営業利益率が10%以上あるか
- ROICが業界平均を上回っており、かつ10%以上あるか
企業の稼ぎ方が効率的であれば、好景気のときに生み出した多くの利益を、成長投資や研究開発に再投資しやすく、さらなる成長や将来の増配につなげやすくなります。
また、利益率が高いことで、不況時にある程度の利益を削っても黒字を維持しやすく、減配リスクを抑えることができます。
このように、営業利益率やROICが高い企業は「景気が良いときも悪いときも強い」構造を持っており、長期的に安定した高配当が期待できるのです。
営業利益率で「粗利をどれだけ残せているか」を見る
営業利益率は、「売上に対して、どれだけ利益を残せているか」を示す効率性の指標です。
たとえば Apple は、iPhoneのブランド力と高価格戦略によって高い利益率を維持しています。
同じスマホ業界でも、低価格で大量販売する企業に比べて1台あたりの利益が大きく、少ない販売台数でもしっかり稼げる構造になっているのです。
営業利益率は業界ごとに異なりますが、日本企業の場合は 10%以上あれば十分に優秀とされます。
ちなみに Apple の営業利益率は 30% を超える水準で推移しており、世界的に見てもトップクラスの効率性を誇っています。
営業利益率の計算方法
営業利益率 (%) = 営業利益/売上高 x 100
営業利益 = 売上高 – 売上原価 – 販売費および一般管理費
- 売上高から売上原価・販売費・一般管理費を差し引いたものが「営業利益」です。
- つまり、「売上に対してどれだけ本業で利益を残せているか」の割合を示す指標です。
- 製造業など原価がかかるビジネスで特に注目されます。
売上原価は材料費や生産に費やした製造人件費、販売費および一般管理費は広告宣伝費や間接部門の人件費や消耗品費などが含まれます。
ROICで「投下資本をどれだけ効率的に使えているか」を見る
ROICとは、企業が調達した資本(自己資本+有利子負債など)をどれだけ効率よく使って利益を生み出しているかを示す指標です。
資本効率が高い企業は、少ない元手で大きな利益を出すことができ、持続的な成長が期待できます。
Appleは自社で工場を持たず、製造はFoxconnのような外部企業に委託しています。
このように、巨額の設備投資を抑えつつも製品を供給できる体制を構築しているため、投下資本あたりのリターン(ROIC)が非常に高く、資本効率の面でも優れた経営を行っています。
ROICが10%以上あれば、一般的に資本効率の良い企業とされますが、業界によって基準が異なるため、同業他社との比較も重要です。
なお、Apple のROICは 60% を超える水準で推移しており、世界的トップクラスの効率性です。
ROIC(%) = 税引後営業利益/投下資本 × 100
- 税引後営業利益 = 営業利益 × (1 − 実効税率)
- 投下資本 = 有利子負債 + 株主資本(≒総資本)
ROE(自己資本利益率)は株主資本だけを見るため、M&Aなどで負債が増えている企業では実態を過大評価してしまう場合があります。
一方ROICは、有利子負債も含めた「全体の資本に対する稼ぎ」を見るため、資本効率をより正確に評価できる指標です。
特にM&Aを活用して成長している企業や、大きな設備投資を行っている企業ではROICを見ることが重要です。
| 観点 | 営業利益率 | ROIC |
|---|---|---|
| 着目点 | 売上ベースの収益性 | 資本ベースの収益性 |
| 測るもの | 本業の「稼ぎ方の効率」 | 投下資本の「使い方の効率」 |
| 関連領域 | 商品力・価格戦略・販管費コントロール | 設備投資・資本政策・資産効率化 |
| 使用場面 | 競合とのビジネスモデル比較 | 経営の質や投資判断に活用 |
財務は健全か?利息支払能力と自己資本比率の両面で確認
高配当株投資では、利回りの高さだけでなく、企業が今後も安定して事業を継続し、継続的に配当を出し続けられるかどうかが重要です。
その判断材料のひとつが、財務の健全性や借金の返済能力。
本セクションでは、以下の2つの視点から企業の財務状態をチェックします:
- 動的な視点:利息支払いに十分な余裕があるか(利息支払能力比率)
- 静的な視点:財務構造が安定しているか(自己資本比率)
- 利息支払能力比率は2倍を上回っており(20倍以上なら極めて健全)、かつ業界平均以上あるか
- 自己資本比率は40%以上、かつ業界平均以上あるか
利息支払能力比率(インタレスト・カバレッジ・レシオ)
企業が借入金に対してどれだけ余裕を持って利息を支払えているかを示すのが、利息支払能力比率です。これは次のように計算されます:
利息支払い能力比率 =(営業利益 + 受取利息 + 受取配当金) ÷(支払利息 + 割引料)
たとえば、利息支払能力比率が20倍であれば、利息の20倍の利益を出していることになります。
数値が大きいほど返済に余裕があり、2倍以上あれば一定の安全圏、20倍以上であれば非常に健全な状態と評価されます。
一方で、この指標が1倍を下回る場合は要注意です。営業利益などの稼ぎだけでは利息支払いが賄えず、資産の売却や借入の借換えに頼っている可能性があるからです。
高配当株投資では、利息支払能力比率が2倍以上かつ業界平均以上であるかを一つの判断軸としましょう。
自己資本比率
自己資本比率は、企業の総資産のうち、どれだけが株主資本(返済不要の資本)によって構成されているかを示す指標です。
「自己資本 ÷ 総資産 × 100」で算出され、40%以上あれば一般的に健全とされます。
特に日本企業全体の平均は約43%、製造業は51%、卸売業や小売業はそれぞれ40%台という水準なので、業界平均と比較して高いかどうかも意識しましょう。
この比率が高いほど、借入に依存せずに安定して事業を続けられる体力があると評価できます。
逆に比率が低すぎると、景気の悪化や金利上昇による返済負担の影響を受けやすく、減配や財務悪化のリスクが高まるので注意が必要です。
配当の余力はあるか?配当性向とFCFで二重チェック
企業が長期的に安定して配当を出し続けられるかを見極めるには、「どれだけの余力をもって配当しているか」の確認が欠かせません。
その配当余力を測るには、帳簿上の利益に対する配当の割合(配当性向)に加え、現金ベースでの余力(キャッシュ配当性向)にも注目するのが有効です。
- 配当性向(EPSベース)は40〜50%以下か
- キャッシュ配当性向(FCFベース)が100%を下回っているか
配当性向(EPSベース)で帳簿上の余力を見る
配当性向(EPSベース)は、「企業が稼いだ純利益のうち、どれだけを配当に回しているか」を示す指標です。
おおよそ40〜50%以下であれば、無理なく配当を出せている状態といえます。
一方で、配当性向が100%を超える状態とは、利益を上回る額の配当を支払っていることを意味します。この場合、内部留保や将来投資の余地がないだけでなく、自己資本を削ってまで配当している状態とも言え、持続可能性に疑問が生じます。
配当性向の計算式
配当性向(%)= 1株あたりの配当額 ÷ 1株あたりの当期純利益 × 100
配当性向が高いことによる注意点
- 利益のすべてを配当に回している(=配当性向100%)場合、それ以上の増配は難しい
- 将来の成長に向けた投資余力が不足する
- 一時的な利益減少や突発的な支出に対する備えがない
- 資本を取り崩して配当を続けている可能性もあり、持続性に欠ける
ただし、コロナ禍のように一時的に利益が大幅に減ることで100%を超える年もあり得るため、それが継続的な傾向かは確認しましょう。
私の場合、一時的なものであれば受け入れ可能と判断する場合もあります。
キャッシュ配当性向(FCFベース)で現金余力を測る
帳簿上の利益だけでは、企業の「配当の持続性」は見抜けません。
そこで注目すべきなのが、FCF(フリーキャッシュフロー)に対してどれだけ配当しているかという視点です。
それを確認する際にはキャッシュ配当性向という指標を使うと便利です。
キャッシュ配当性向(%)= 配当総額 ÷ フリーキャッシュフロー(FCF) × 100
企業がどれだけ利益を上げていても、現金がなければ配当は続けられません。
キャッシュ配当性向が100%を超える状態は、FCFを上回る配当を出している=手元資金を削って支払っていると見なされ、継続性にリスクが伴います。
反対に、キャッシュ配当性向が100%未満であれば、本業の稼ぎの範囲内で配当を賄えていると評価できます。
株主還元の方針は明確か?配当方針や自社株買いをIRで確認
企業が長期的に安定した株主還元を行う意思を持っているかも重要なチェックポイントです。
株主還元の姿勢が明確な企業は、将来にわたって継続的な増配や自社株買いを期待しやすく、より信頼度の高い高配当投資先といえます。
- 配当方針は明確か(例:累進配当・継続的な増配などの記載あり)
- 自社株買いに積極的か(近年の実績や予告の有無)
こうした情報は、企業のIRページや決算説明資料に記載されています。
「{会社名} IR」で検索して、配当や株主還元に関する文言を探してみましょう。
例えば、NTT の株主還元ページでは以下のような記述があります。
株主還元の充実は、当社にとって最も重要な経営課題の1つであり、継続的な増配および機動的な自己株式取得の実施を基本的な考え方としております。
2023年度の年間配当額は、13期連続での増配となる1株当たり年間5.0円(対前年度+0.2円)を予定しております。
これまでの配当額は、2003年度比で見れば10倍まで拡大しています。
このような記載から、企業が株主への利益還元をどれだけ重視しているかが読み取れます。
今後の配当傾向を予測する上でも、IRでの還元方針確認は欠かせません。
自社株買いとは、自社が発行している株を市場から買い戻すことです。
買い戻した株は一般的に「消却」され、発行済み株式数が減ります。
自社株買いで1株あたりの価値が高まる理由
株主にとって自社株買いがプラスに働く主な理由の一つが、EPS(1株あたり純利益)の増加です。EPS は以下の式で表されます:
EPS = 純利益 ÷ 発行済み株式数
この式からもわかるように、自社株買いによって株式を消却し、発行済み株式数が減ると EPS が上昇します。
つまり、1株あたりの利益が増える=1株あたりの価値が高まるという効果があるのです。
EPSが上がると株価はどうなる?
株価の割安度を示す代表的な指標に「PER(株価収益率)」があります:
PER = 株価 ÷ EPS
EPS が上がると、PER が下がり、相対的に割安と判断されることになります。
この「割安感」に注目した投資家の買いが入ると、株価が上昇する可能性があるのです。
※PERが下がっただけで自動的に株価が上がるわけではなく、あくまで投資家に再評価される余地があるという意味です。
自社株買いで配当負担を減らせる
発行済み株式数が減ると、1株あたりの配当額が変わらなくても、支払う総額は減ります。
それによって、将来のフリーキャッシュフローに余裕が生まれます。
その余剰資金は、新たな投資や研究開発に活用できるだけでなく、利益剰余金として蓄積され、結果的に自己資本比率の向上にもつながります。
自社株買いに関する楽天証券の記事がわかりやすので、より詳しい情報を知りたい方はご参照ください。
不況でも減配せず乗り越えられるか?リーマン・コロナ期の推移で確認
企業の配当姿勢は、順調な時だけでなく厳しい時期にどう対応したかにも表れます。
たとえ足元の業績が好調で配当利回りが高くても、過去の不況時にすぐに減配していたような企業であれば、今後も同様の対応を取る可能性があります。
だからこそ、企業が逆風の中でも安定的に配当を出し続けたかを確認しておくことはとても大切です。
過去の危機的な年でも減配せずに乗り越えた実績があるか
- 2008年:リーマンショック
- 2011年:東日本大震災
- 2020年:コロナショック
今後も不測の事態は起こりうるからこそ、こうした局面での配当実績を確認することで、その企業の「配当を守る力」を測りましょう。
ステップ3|2つの条件が揃った買い時に優良株を購入する
ステップ2までで、長期保有にふさわしい優良高配当株を絞り込めました。
高配当株投資では「優良高配当株を適切なタイミング(株価)で購入する」ことが、長期的なリターンに直結します。
そのため、ステップ3では2つの買い時の判断基準をご紹介します。
優良高配当株の株価が「配当金 ÷ 4%」より低くなった時が買い時
高配当株投資では「配当利回りが高い銘柄から探す」のではなく、あらかじめ選んだ優良高配当株が、配当利回り4%以上になるタイミングで買うことが重要です。
この順序を間違えると、利回りは高くても業績が不安定な「罠銘柄」をつかむリスクがあります。
配当利回り (%) = 1株あたり配当金 ÷ 株価 × 100
ただし、都度配当利回りを計算するのは面倒です。
そのため、配当利回り4%となる価格を優良高配当株ごとに計算し、株価がその水準を下回ったときに購入する、という判断基準を持っておくと便利です。
優良高配当株の株価が「配当金 ÷ 0.04(4%)」より低いか
たとえば、配当金が40円の銘柄なら、株価が1000円以下になったら買い時。
株価がこの水準まで下がるのをじっくり待つことが、長期的に高い配当リターンを得るコツです。
一度購入してしまえば、数十年にわたって「利回り4%以上」の土台を築けることになります。
また、このような基準を決めておくことで、株式市場が一時的に暴落したときにも、冷静に「買い時」を判断する指針となります。
PER・PBRを使って株価が割安な時を見極めて買う
高配当株投資では、「今の株価が企業の純利益や純資産に対して割安かどうか」も買い時の判断材料です。この判断には、PER(Price Earning Ratio: 株価収益率)や PBR(Price Book-value Ratio: 株価純資産倍率) を使うのが便利です。
PER・PBR が過去5〜10年の水準と比べて相対的に低いか
- PER = 株価 ÷ EPS(1株あたりの純利益)
- PBR = 株価 ÷ BPS(1株あたりの純資産)
PERは株価が利益の何倍か、PBRは株価が純資産の何倍かを表しています。これらの数値が低いほど、相対的に「割安」と判断される傾向があります。
株価の高低だけで判断してしまうと、企業の利益や資産の成長が反映されず、正確な割安判断ができません。
過去5〜10年ほどのPERやPBRと現在の水準を比べ、「割安感があるかどうか」をざっくりでもチェックしておくとよいでしょう。
なお、私自身もこの判断はグラフを使って目視でざっくり行っています。
将来的には、TradingViewなどを使ってPERやPBRの過去平均を自動で可視化する仕組みも検討中です。
まとめ | 3ステップで罠銘柄を避け、優良高配当株を買い時に買おう
高配当株投資は、配当利回りの数字だけを見て飛びつくと「罠銘柄」をつかむリスクがあります。
大事なのは、「優良な企業かどうか」を見極めたうえで、「割安なタイミングで購入する」こと。
本記事では、そのための実践的なフレームワークとして、以下の3ステップを紹介しました。
- Step 13 つの必須条件でサッと選別
- 過去10年以上配当金が維持・上昇傾向
- EPSが長期的(5〜10年以上)に上昇傾向
- BPSが長期的(5〜10年以上)に上昇傾向
- Step 26つの望ましい条件で長期保有向け優良株を見極める
- 本業でしっかり稼げているか?
- 営業CFが直近5〜10年で上昇傾向
- 稼ぎ方の効率は高いか?
- 営業利益率が10%以上
- ROICが業界平均以上、かつ10%以上
- 財務は健全か?
- 利息支払能力比率が2倍以上、かつ業界平均以上
- 自己資本比率が40%以上、かつ業界平均以上
- 配当の余力はあるか?
- 配当性向は40〜50%以下
- キャッシュ配当性向が100%未満か
- 株主還元の方針は明確か?
- 累進配当・継続的な増配など配当方針が明確
- 自社株買いに積極的
- リーマン・コロナなど危機時も減配せず乗り越えた実績があるか
- 本業でしっかり稼げているか?
- Step 32つの条件が揃った買い時に優良株を購入
- 株価が「配当金 ÷ 0.04(4%)」より低い時
- PER・PBR が過去5〜10年より相対的に低い時
このステップを踏むことで、次のような投資判断ができるようになります:
- 一見利回りが高くても危ない罠銘柄を避けられる
- 長期で保有しても安心できる企業だけを選べる
- 市場が冷え込んだときでも、焦らず「買い時」を判断できる
つまり、高配当株投資を「再現性のある戦略」として実行できるようになるのです。
銘柄選びに迷っている方、利回りの高さに不安を感じたことがある方は、ぜひ本記事の3ステップをベースにご自身の判断軸を整理してみてください。
なお、私もまだまだ修行中の身なので今後も分析方針や投資方針は変更する可能性があります。
また、投資は自己責任という前提のもと、ご自身の判断で本コンテンツをご活用ください。
📚 次に読みたいおすすめ記事
1. 分析を効率化したい人へ
今回紹介した分析フレームワークを、より短時間で実践するためのツール活用術を解説します。
2. 少額から始めるならこれ
単元未満株(S株)を使えば、少ない資金でも分散投資が可能に。高配当株投資の第一歩に。
3. 高配当株投資をもっと学ぶなら
インデックス投資との違いや併用メリットなど、高配当株投資の全体像を整理したい方はこちら。
参考書籍
高配当株投資について更に知識を深めたいときには、以下の参考書籍を読んでみてください。
1つ目はこちら。高配当株投資を始めるきっかけとなった本です。
ド素人の頃から初めて毎月18.5 万円 (222万円/年) の配当金を得るまでの失敗談・試行錯誤や、高配当株の分析方法、永久に保有したい銘柄が分かる良い本です。
同じ筆者の2つ目の書籍です。1冊目よりも内容が濃く深いです。
そのため、1冊目を読んだ後に2冊目を読んだほうがスンナリ入ってくると思います。
上記2書籍を読み、自分で高配当株分析をする際に業界内の立ち位置や売上などを比較する際に便利です。